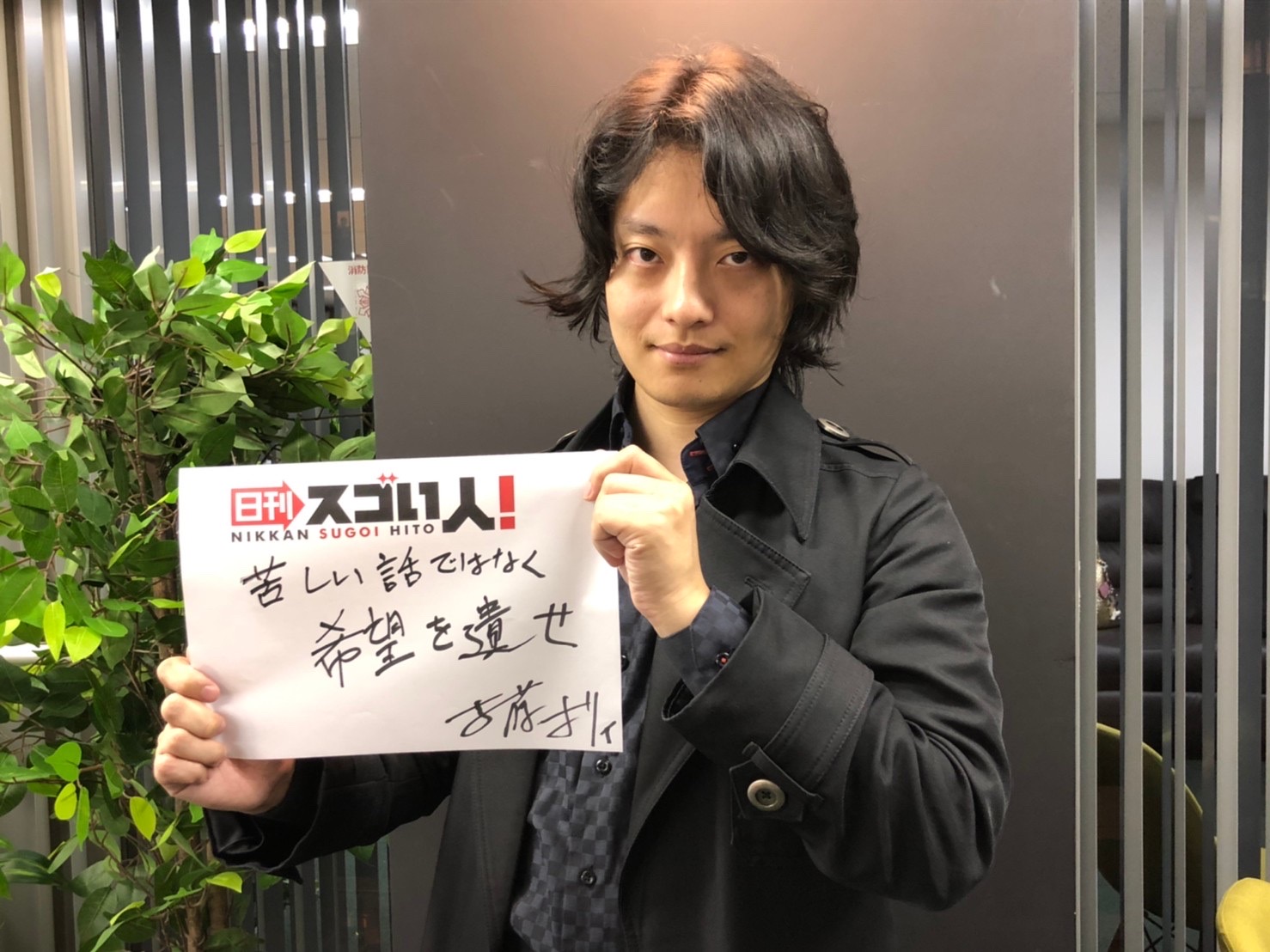
今週ご紹介するのは、OriHime(おりひめ)という分身ロボットで「孤独」の中に暮らす人へ光をもたらし、その「孤独」を消すために日夜戦い続けるスゴい人。20年前には存在しなかった職業、ロボットコミュニケーターとして日夜「会えない人に会いにいく」その方法を考え続けている人である。子供時代に自分が体験した「孤独」の中に、今まさに暮らしている人々へ光を届けようとしている。そのスゴい足跡と熱い想いを4日間お伝えします。さあ、オリィこと、吉藤オリィ様の登場です!
令和リニューアル記念4日連続インタビュー
DAY1
約4年に及ぶ不登校を支えたものづくりの原点
編集部(以下編):本日はよろしくお願いいたします。
吉藤さん(以下吉):よろしくお願いいたします。
編:2016年に取材させていただいてから、4年ぶりの二回目の取材ということになります。
この4年でさらにご活躍の場が広がり、各方面からの期待もますます高まっているのではないでしょうか。
吉:そうですね、ありがたいことにTVなどのメディアでの露出も増えてきましたし、何よりもOriHime自体の認知度が上がって、分身ロボットが何をする存在なのかが知られるようになってきたことには嬉しさがあります。
編:前回の取材の時に小学校5年生から中学2年生までの約4年、不登校を経験したお話を伺いました。その時の経験が今も吉藤さんにとって大きな支えとなっているということにお変わりはないですか?
吉:そうですね。祖父母が教えてくれた折り紙が私を夢中にしたし、環境的に孤独だった私に孤独を忘れさせてくれるほど没頭できる時間でしたから。学校で運動も勉強も得意ではなかった私にとっては唯一の誰にも負けない、人に自慢できる特技でしたね。
編:学校でも折り紙はなさっていたのですか?
吉:やってましたけど、学校でのいわゆる「折り紙」という枠組みには私は合わなくて。そもそもが創作折り紙でしたから。折り目もつけないし、自分の感覚だけで折っていく独自のやり方ですからね。机の上で、折り目を付けたり、広げたりして、マニュアル通りに形のあるゴールを目指していくいわゆる折り紙というのは逆に苦手だったんです。
編:集団行動みたいなものが苦手でいらしたんですよね。
吉:そう。決められた作業的なものというのは全然面白くなかった。小学校5年生くらいには15時間くらいかけて創作折り紙を折っていたんです。
結果的にこの折り紙の体験が今につながるものづくりの原点であることは間違いないんですけどね。
編:その不登校を脱するきっかけを作ってくれたのがお母さまでいらしたんですよね
吉:そうです。不登校だったので家で折り紙をしたり、ゲームをしたりという生活だったのですが、母が突然ロボットコンテストに申し込んだと。もともとロボット自体は興味があったので挑戦してみたのが最初です。
編:お母さまはロボット作りの才能を見出していらしたんですか?
吉:これは母親がね、私がもともと折り紙が好きだったので、折り紙を折れる子はきっとなんか理系の頭を持っているんじゃないか?って思ったということなんです。
最近でこそ折り紙ってすごく理数の象徴的な趣味というイメージがあるかもしれませんけど当時は全然そういうことなくて。
だから小学校とかになっても折り紙やってるっていうのはこの子大丈夫かしらっていうのを親が思う、今でいうおままごとを大きくなってもやっているみたいな、そんなイメージなんですよ。周りからもそういうことやっていて恥ずかしくないのと言われていたようなそういう時代でした。そんな時に母が折り紙に向かっている私が、ロボット作りというかものづくりに向いてるだろうからと、大会に申し込んでおいたから行ってこいと。それが中学校一年生の時でしたね。
編:もともと向いてらしたんですかねそういうものづくりとかに 
吉: 向いてはいましたね。黙々と一人で何か作業をするというのがすごく好きだったので。どちらかというと人と話すのが苦手だったんですよ。人と話すことに価値を見出せなかったですから。そんな自分にとって創作活動というかひたすら何かを作るということは非常に向いていたと思いますね。
編:実際にロボット作りを通してその魅力を認識されたのでしょうか?
吉:正直なところロボット作りの魅力はあまり考えたことないですね。ものづくりの楽しさというのはどこか本質的に同じで、私が魅力を感じていたのは当時は折り紙ですから。そして折り紙が面白かったのには2つ理由がありまして。
一つは単純に折って形をつくるという作業それ自体が楽しいという単純な好奇心の部分と、もう一つはその時は勉強もできないし友達もいなかったので折り紙しかすることがなかったから、折り紙をすることによって唯一人から認められる。人からすごいと言ってもらえるめちゃくちゃ貴重な承認の瞬間が折り紙しかなかったっていう現実的な部分。
物作りもある意味それの延長線上。だから他に人に誇れることなんか何もないのだけれども物作りだけはちょっと人よりも自信があったかなと。それがロボット作りにも生かされたというのが正しいかな。
編:それでも大会で優勝をされたのはやはりロボットには才能がおありだったということですよね。
吉:その大会は市販の虫型のロボットを組み立ててプログラミングしてゴールタイムを競うという内容だったのですが、私以外の参加者はたぶん学校で勉強ができそうな頭よさそうに見えたし、正面からプログラミングで戦っても勝ち目がなさそうだったから、考えるよりも先に動いて結論を目指したんです。ロボットの足をみんな変形させていたのですが、僕は最初の形のままで臨んだり、みんながいろいろと考えを巡らせている時間を使って僕はひたすら実際にロボットを走らせてトライ&エラーを積み上げて、絶対性能を高めました。とにかくみんながやっていそうなことはやらなかったんです。
編:そして優勝。
吉:ここでの優勝をきっかけに大阪であった全国規模の大会に各退会での優勝者の一人として出場権を得まして、惜しくも準優勝しました。優勝と2位の差を知りましたし、その悔しさというのも実感しました。
編:シンプルに自分が人に誇れるものを突き詰めて、結果が出たということですか?
吉:当時の僕にとってはものづくりは唯一のコミュニケーション手段だったんですよね。不登校時代というのは理解者もいなくて本当に苦しかったんです。俺はいない方がいいんじゃないかと。自分は誰からも必要とされていないし、自分なんかいないほうがと思ったこともある。どうやったら自分を好きになれるかってことを考えていました。目が覚めたら勝手に池の前に立ったことがあって、あー体が死にたがっているんだと思ったとき、必死に死なない理由を探しました。そんなときに折り紙とかバルーンを作って喜んでもらえると生きててよかったって心底思えた。ものづくりは社会とつながることのできる、すごく大事なコミュニケーションツールだったんです。
編:褒められることで自分の存在意義を確認していた。
吉:ある意味ね。これは私の持論なんですけど「褒められるまでのコスト」という考え方なんだけど。あまり躊躇なく困っている人をパッと見て手助けができる人や、「何かお困りですか。」と声をかけられる人とか、「これやっといたよ。」というような気配りとかできる人たちは、褒められるまでの対価が低いんですよ。クラスで面白い話ができるような人気者とかもね。
編:褒められるところまで行くまでにかかる時間をコストと考えるわけですね。
吉:僕は絵を描くのも好きだったんですよね。でも、すごい!って言ってもらうためにはただの絵を描くだけではダメで。すごい!って言ってもらえるようなレベルの絵や複雑な作品を作って初めてすごい!って言ってもらえるんだけど、その見た人も「お前よくこんなの作れるな」とは言ってくれるけどそれ以上の言葉は出てこない。でもその言葉が欲しいから、その人からすごい!をもらうためにはよりワンランク上のものを作る必要がある。これはねなんか承認欲求を満たす唯一の手段としてやっていた感はあったかなとは思いますよね。
編:なるほど。
吉:そうはいってもテレビなんかで折り紙選手権みたいな番組があって、明らかに自分よりはるかにすごい人がいるって事実を知るわけですよ。自分には折り紙しかないのに、自分なんか足元にも及ばないような人がたくさんいる現実。その時は一回折り紙やめました。面白そうだなと思ってバルーンアートをやった時もありました。それで面白い発見があったんです。これはコスパがいいんですよ。
編:褒められコスパが高い?
吉:そう。折り紙って一つの作品作るのに地味な作業を繰り返して何分もかけて作ってやっとすごいと言ってもらえる世界なんだけど、バルーンアートはプロセスもすごいって言ってもらえる。シュッシュと空気入れて、バルーンが膨らむプロセスも見てる子供たちがわくわくするし、きゅっと音が出て結んだり回したりして1分くらいで作品ができる。
バルーンでも時間がかかる犬とかよりも20秒くらいで作れる剣のほうが目の前の子供たちが喜ぶんですよ。特にすごい事をしてるわけではないんだけど、すごい!っと言ってもらえる部分というのはなんていうか、そこにかけた労力そのものではなくて、単純にエンタメとしてどう感じるかという部分は強いなと、ものづくりをするクリエイターとしての不条理を感じたりしましたね。
ここで得られた教訓は、本人が苦労しても認めてもらえない事が多々ある一方で、そこまで苦労していない事がすごいと言われる事もある、という事です(笑)
明日は、このように葛藤もあった幼少時代から、まるで運命に導かれるようにロボット制作の道へと続いた人生の軌跡を伺います。
取材:アレス 構成:Noriko 翻訳(英):Tim Wendland
株式会社オリィ研究所♦"個人向けOriHime Lite"キャンペーン実施中
分身ロボットで、大切な人と素敵な時間を☆
♦著書 「孤独」は消せる。サンマーク出版 (2017)









